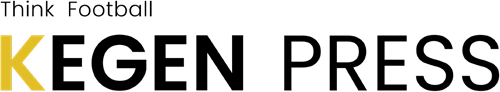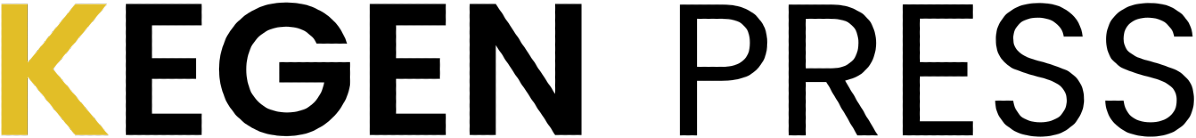訪れてみたい! “サッカー侍”が戦った街 ― マルセイユ(フランス)

| 日本サッカーの成長とともに、いまや日本人選手の海外移籍は後をたたない。それはヨーロッパのみならず、世界各国に及んでいる。そんな“サッカー侍”たちが、かつて戦った街がある。いま戦っている街がある。それだけで、「いつか訪れてみたい…」。そう思わせる魅力がある。 |
トルシエ氏との師弟関係が縁で、2005年に中田浩二が渡った
フランス南部にある港湾都市マルセイユ。この街で戦った「侍」といってすぐに思いつくのは、名門オリンピック・マルセイユに在籍した酒井宏樹(2016-21年)と長友佑都(2020-21年)だろう。日本代表の両サイドバックが同時にプレーした街だ。

だが、印象に残るのは元鹿島アントラーズの中田浩二かもしれない。元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏に誘われ、2005年1月に移籍。パイオニア精神で渡仏した中田は、自身初の海外挑戦の舞台にこの街を選んだ。
守備的MFだった中田は日本代表でDFにコンバート。トルシエ氏の代名詞「フラット3」システムに欠かせない選手として、「トルシエの申し子」と呼ばれ、2002年のワールドカップなどで活躍した。そのトルシエ氏がマルセイユの監督時代に、引き抜かれた。日本代表時代の師弟関係が縁で実現した名門クラブへの移籍。また、当時は珍しかった日本人DFの欧州挑戦。期待感しかなかった。
しかし、2005年3月に公式戦デビューを果たすも、6月に成績不振でトルシエ氏が解任。翌シーズンは出場機会が激減し、2006年1月にスイスのFCバーゼルへ移籍した。公式戦出場は15試合と不遇なフランス生活だったといえる。だが、フランク・リベリーやサミル・ナスリなど、のちにフランス代表の中核となる選手たちと同僚としてプレー。その経験は日本サッカーに還元された。
古代ギリシア人が築いた「フランス最古で最大の港湾都市」
地中海に面したプロヴァンス地方にあるマルセイユは、「フランス最古にして最大の港湾都市」と呼ばれ、古くから貿易の中心地として栄えた。人口約87万人はパリ(約217万人)に次ぐ国内2番目(2018年の統計)。パリのリヨン駅からは高速列車(TGV)で約3時間の距離だ。温暖な地中海性気候はブドウ栽培に適し、ワイン造りが盛んな地域でもある。

その歴史は古く、紀元前6世紀ごろに古代ギリシア人が築いた植民市「マッサリア」が起源だ。その後はローマ帝国の支配下で発展し、10世紀にプロヴァンス伯領となり、15世紀後半にフランス王国に併合された。マルセイユの地名は、マッサリア(フェニキア語)のラテン語訳「マッシリア (Massilia)」に由来する。
ちなみに、フランス国歌が「ラ・マルセイエーズ(マルセイユの歌)」と呼ばれるのは、フランス革命時にマルセイユの義勇兵が革命歌として口ずさみながら、パリに入城したためだ。当時のパリ市民の間で流行し、その後、国歌となった。
■「ヨーロッパの玄関口」として大貿易港に。移民が多く住む
2600年余りの歴史の中で、大貿易港としての地位を確立したのは19世紀以降。北アフリカの植民地化政策における進出拠点になったことや、1869年にスエズ運河が開通し、地中海貿易がさらに活発化したことが大きな要因だ。
アフリカや中東、アジアをつなぐヨーロッパの玄関口として、その重要性はさらに増し、19世紀半ばに大規模な新港を建設。港湾施設の拡張とともに商工業も発達した。
一方、世界中から人々が集まるため、移民が多く住み、異なる民族や文化が混在する。マルセイユで生まれ、かつてフランス代表のスター選手だったジネディーヌ・ジダンの両親はアルジェリア移民で知られる。彼自身は「北アフリカ移民の星」と称され、象徴的な存在だった。
シンボルは街を見守る大聖堂 『巌窟王』の舞台、イフ島の城塞が残る
街の中心に位置する旧港は、市民や観光客が集まるメインスポット。昔ながらの「港町」の面影がいまも残る。貿易の拠点が新港に移り、現在は小型の漁船やヨットが数多く停泊する。朝には魚市が開かれ、とれたての新鮮な魚が並ぶ。
旧港の南にある小高い丘の上に建つ「ノートルダム・ド・ラ・ガルド聖堂」は街のシンボルだ。

19世紀半ばに建てられたローマ・ビザンチン様式の聖堂で、鐘楼の上には幼いキリストを抱いた黄金のマリア像が立ち、海に出る船乗りたちを見守ってきた。マルセイユっ子たちは親しみを込めて「ラ・ボンヌ・メール(優しい聖母さま)」と呼ぶ。ここから眺めるマルセイユの街は絶景だ。
旧港から船で20分ほどの沖合いにあるイフ島には、16世紀に築かれた城塞「シャトー・ディフ」が現存する。政治犯の監獄として使われ、アレクサンドル・デュマ・ペールの小説『モンテ・クリスト伯』(日本では『巌窟王(がんくつおう)』の題名で知られる)の舞台として描かれ有名に。現在は人気の観光スポットとなっている。


名物「ブイヤベース」は、漁師が売れ残った魚を煮たのが始まり
「ブイヤベース(bouillabaisse)」といえば、フランスの寄せ鍋料理だが、マルセイユが発祥だ。
魚市で売れ残った魚や、売り物にならなかった魚を、漁師たちが大鍋で塩と煮込んだのが始まりだという。よって、「bouillir(煮込む)」と「abaisser(下げる、減らす)」を合わせたのが語源。つまり、「煮込んで(かさを)下げる=煮込み続ける」という意味である。
17世紀に新大陸からトマトが伝来すると食材として取り入れられたり、また香料が加えられたりと、時代とともにアレンジされ、レシピが確立。本場のブイヤベースは、スープと中身が別々に出されるのが一般的だという。

マルセイユが観光地化すると、多くのレストランでふるまわれ、いまや観光客向けの高級料理に。そのため、市は1980年に「ブイヤベース憲章」を制定。食材にできる魚(地中海沿岸の岩礁魚)や野菜などを細かく定め、伝統を守っている。
特産のプロヴァンス・ワインとの相性が抜群だという名物ブイヤベース。憲章を掲げる公認のレストランで、ぜひ本場を味わってみたい。