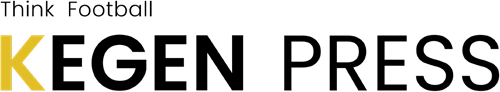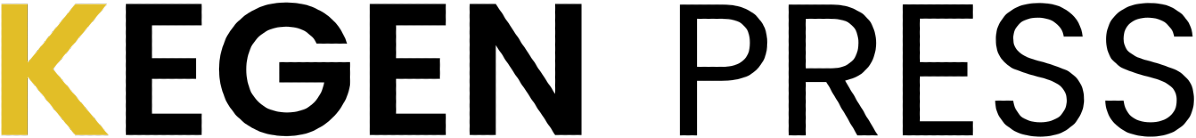なでしこ初の外国人監督ニールセン氏 人選のカギは「敵を知る」経験値

サッカー女子日本代表(なでしこジャパン)に“待望”の初外国人監督が誕生した。デンマーク自治領グリーンランド出身のニルス・ニールセン氏(53)だ。
ニールセン氏は20歳ごろに腰の怪我でサッカー選手の道を諦め、指導者になった。デンマークの国内クラブで長く育成年代の指導に携わり、2006年頃から同国の各アンダー世代監督や女子フル代表監督などを歴任。2017年UEFA欧州女子選手権でデンマークを準優勝に導き、注目を浴びた。
その手腕が高く評価され、2018年から2022年までスイス女子代表を指揮。2023年5月からイングランドの名門マンチェスター・シティ(マンC)の女子テクニカルダイレクターに就いたが、指導者への復帰を強く望み今年6月に辞任。フリーになっていたところ、日本サッカー協会(JFA)からのオファーを受けたという。
“意識改革”の必要性を強調 「自信、勇気をもつことが大切」
欧州では有名なニールセン氏だが、日本ではあまり知られていなかった。だからこそ気になるのは「なでしこジャパンでどんなサッカーを目指すのか」だ。
12月18日の就任会見で、記者がサッカーファンの思いを代弁して質問した。しかし、ニールセン氏から明確な回答はなかった。「強みをさらに伸ばす」や「惜しかったで終わらないために勝つための議論をスタッフとする」など漠然とした内容が多く、よく分からなかったのが正直な感想だ。
一方、終始強調したのはメンタルの部分。
「目標達成には自信を持つことが大切だ」「大事な瞬間に勇気をもってチャンスをつかみに行く強い心が必要だ」などと力説。なでしこのプレーに物足りなさを感じているようだ。自信の無さをただ感じているだけなのか、それとも「闘志が足りない」と言いたかったのか。どちらにせよ、チーム全体として“意識改革”をはかる意向を強調した。
また「自らの意見は率直に伝える」のがモットーで、忌憚(きたん)のない姿勢で選手と「対話」していくという。「率直に伝えなければ選手は伸びない」と持論を語った。
池田前体制は「継続重視」 ニールセン新体制は「ゼロ出発」
就任会見で分かったのはニールセン新体制は「未知数」だということ。JFAはゼロベースでのチーム再構築にかじを切った。
思い出されるのは、前任の池田太氏の監督就任会見だ。
前々任の高倉麻子氏の退任から後任決定に2か月余りを要したことについて、当時の今井純子・女子委員長は「東京五輪の総括をずっとしていた。新たにゼロベースでやるべきか、いままで継続してきたものを極めるべきかを話し合った」と説明。その上で「目指してきた方向性自体は間違っていない」と結論づけ、「継続」を選んだことを明かした。

つまり、池田前監督の目標は「高倉体制をベースに細部を詰め、世界王座を奪還すること」だった。高倉氏の在任期間は5年余り、池田氏は3年弱。目標達成はならず、約8年の時間が流れた。
一方、ニールセン氏の就任会見で池田体制の総括についてはあまり語られていない。
佐々木則夫・女子委員長が「選手に気持ちよくサッカーに打ち込ませる空気感はすごくよかった。しかし、もっと積極的に鼓動させ、ベスト8の壁を打ち破ってファイナルへ進む。それが成し遂げられなかった」と話したぐらいだ。
佐々木氏は「(これまでは)戦術的な要素、日本女性特有の協調性豊かなサッカーができる点を踏まえ、日本人の指導者がいいと考えてきた」と説明。“リスタート感”の強い就任会見を印象づけた。
女子W杯、五輪大会で指揮経験なし 選んだ本当の理由は?
ニールセン氏を選んだ本当の理由はどこにあるのか。
佐々木氏は豊かな人間性と人柄の良さが決め手だったと強調したが、そこは必要最低限の資質。「未知数」な監督だけにもっとほかに理由があるはずだ。
宮本恒靖会長が説明した3つの判断材料は、①国際大会の経験があること、②日本の女子サッカーと選手を熟知していること、③今後の日本女子サッカーの発展がどうあるべきかをイメージできること。
長谷川唯、清水梨紗ら現在4人の日本人選手を有するマンチェスター・シティの女子技術部門トップだった点でいえば、②は問題ない。③は交渉段階で明確になったのだろう。
①はどうなのか。ニールセン氏は、FIFA女子ワールドカップ(W杯)や夏季オリンピック(五輪)などの世界大会で指揮を執った経験がないという。

既述のとおり、2017年欧州選手権のデンマーク準優勝で注目を浴びたが、2019年FIFA女子W杯予選はオランダとのプレーオフに敗れ、あと一歩のところで本大会出場を逃している。
スイス代表時代は、2023年FIFA女子W杯予選をプレーオフの末に勝ち抜いたものの、本大会を前に家庭の事情を理由に退任した。
ニールセン氏について調べたが、女子W杯欧州予選や欧州女子選手権を通じて相当数の試合を指揮している。重圧のかかったプレーオフも経験済みだ。しかし、確かに世界大会の経験はなかった。
それなら、なぜ選んだのか。逆にニールセン氏でなけらばならない理由を考えてみると、ようやくその理由がみえてきた。
欧米女子サッカーを熟知 「敵を知る」ニールセン氏の経験値
中国春秋時代に書かれた『孫子』と呼ばれる兵法書に、「彼を知り己を知れば百戦殆(あや)うからず」という言葉がある。
「まず敵を知り、その上で味方を知って戦えば、何度戦っても敗れることはない」という意味だ。敵を知らず、味方だけ知っていてもダメ。敵と味方の優劣、長短をよく理解することが大切だという格言である。
世界一になってから、なでしこジャパンはその強みのパスサッカーに磨きをかけることに重きを置いてきた印象がある。選手の技術は世界で通用する。パスサッカーの質を高めれば、相手が誰であろうと勝てる、と。
高倉、池田両体制の時代、選手層は申し分なかった。王座奪還の期待感もあった。だが、選手のレベルが上がっても、「海外組」が増えても、結果は伴わなかった。
振り返れば、近年のなでしこジャパンに立ちはだかった「壁」は体格に勝る欧米の強豪国だ。
2019年女子W杯は16強でオランダに敗戦。2021年東京五輪、23年女子W杯はいずれも8強でスウェーデンに敗れた。2024年パリ五輪は16強でアメリカに惜敗。予選リーグでスペインに逆転負けし2位通過したことも響いた。
欧米の女子サッカーが著しく成長を遂げるなか、やや「自己研鑽」に目を向けすぎた感は否めない。
そう考えると、欧州強豪国との戦い方、その準備を知るニールセン氏の経験値と知恵は大いに活かせる。マンC時代の経験をふまえれば、欧米の女子サッカーと強豪各国を熟知する指導者だ。
「敵を知る」経験値。人選の狙いはきっとここにある。
うまくいっても、いかなくても、なでしこ史上初の外国人監督がもたらす「変化」は代えがたい「収穫」だ。世界王座の奪還は待ち遠しいが、ゼロベースならチーム作りを焦る必要はない。着実な進化を期待したい。
(了)